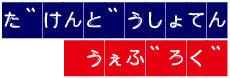« 角田光代『人生ベストテン』○ | Blog Top | 更新情報 »
April 04, 2005
西川祐子『住まいと家族をめぐる物語』○
サブタイトルは〈男の家、女の家、性別のない部屋〉。
家父長が家のすべてを取りしきった「男の家」から、不在の男にかわって主婦が管理する「女の家」へ。家族それぞれがじぶんの部屋を持って個別の生活を営み始め、やがて性別の希薄なワンルームの時代へと移り変わった。高齢者や子どもの居場所はどこにあるのか。日本近・現代140年の歴史を読み解き、けっして悲観的ではないアプローチを試みる。
じぶんだけの部屋がほしいと親に言いつのった記憶がある。わたしが小学生のころ、完全な個室を与えられている子供はまれであった。社会全体に「個室はよくない」という空気があったことはいうまでもない。なぜそうだったのかということが本書を読むとよくわかる。
関連して、日本の会社のシマと呼ばれる机の並べ方を思った。必ずエライ人が部下の仕事ぶりを一望できる配置になっている。これも「男の家」、つまり家父長制の名残ではないのか。
著者は京都文教大学人間学部教授。専攻はジェンダー論および日本とフランスの近・現代文学。「家」の変遷はジェンダー抜きでは語れない。最初から最後まで、これほど熟読できる新書もめずらしい。おすすめ。
★★★★☆(2005.3.28 白犬)
集英社/集英社新書 700円 4-08-720263-1
posted by Kuro : 02:42
trackbacks
このエントリーのトラックバックURL:
http://dakendo.s26.xrea.com/blog/mt-tb.cgi/52
comments
トラックバックありがとうございます。
たしかにオフィスの机の配置というのは家父長制の名残のような感じがしますね。「シマ」という呼び方も、なんだか興味深いところであります。
トラックバックありがとうございます。
たしかにオフィスの机の配置というのは家父長制の名残のような感じがしますね。「シマ」という呼び方も、なんだか興味深いところであります。
投稿者 howe : April 4, 2005 10:36 PM
howeさん。
コメントありがとうございます。
そうですね、いったいいつ頃からあれを「シマ」と呼ぶようになったのでしょうね。
ひとりだけ、背もたれの高い肘掛けつきの椅子にふんぞりかえっているおやじを見ると、わたしはつい信楽焼の大タヌキを連想してしまうんです。はは
あの場所に座るとどういう気分なるのか、えらくなったことがないのでわからないんですけどね。
投稿者 白犬 : April 5, 2005 01:42 AM
コメントをどうぞ。